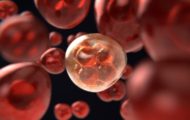目次
子宮がん検診で・・・
1991年5月 実家の母親に
「区のガン検診に行かない?もう あなたも30歳だから受けられるわよ」
(当時、横浜市在住の女性は30歳から子宮ガン検診対象でした)
と言われ、軽い気持ちで はじめて検診を受けました。
その頃、私は冷え症ではあったけれど、それ以外に 持病はなく生理も軽く定期的にあるし
2年前の初産も安産でした。
私にとって ガンという病気は
「自分とは何の関係もない遠いもの」
ガン家系でもなく、健康面で自覚するような不調は 特にありません。
ですから、検診に対して何の不安もありませんでした。
ところが、それから何日後か、1枚のハガキが届きました。
「子宮頸ガン検査について 要精検」 と太字で印刷されていました。
自覚症状がないし、事態がよくわからず、
「どうして、こんなハガキがきたんだろう?」と疑問でしたが
とりあえず、そのハガキを持って 近所の総合病院を受診しました。
「こんなハガキがきたら、ビックリしちゃうよね?。大丈夫だと思うけど、はっきりさせようね」
と産婦人科の医師に言われたのを覚えています。
私も、
「そうか、悪くないことをはっきりさせるために 調べる検査なんだ。」
と自分に都合のいいように解釈して 検査して帰りました。
やっぱり、少し気持ちが重かったので、こんなふうにして吹っ切りたかったのです。
がんの告知・・・
その後、結果を聞きに行くと、検査したときと同じ医師が
「う~ん、良くないんだよねぇ・・」
「え?」
「あのねぇ、子宮頸がんなんですよ。初期だと思いますけど・・・」
「・・・・・?」
医師は、私が一緒に連れていた2歳の長女を見て、メガネをはずして言いました。
「子宮、取っちゃいましょう。 お子さん、もう 1人いるんだし・・・ね、いいでしょう?」
「・・・・・?」
この人、いったい何を言っているんだろう?
子宮だけを取って 済むことではないでしょう?
私は、パーツの集まりではないのに・・・
どうして、がん細胞ができたのか、それをつかまなくちゃ、本当には治らない・・・・
私は、この問題を解かなくっちゃ・・・・・
そんな思いが わ~~っと 一気にものすごい勢いで、私を包みました。
たぶん数秒間だったと思いますが、その溢れ出てくる思いに
私自身が圧倒されそうでした。
手術を拒否して・・・
医師との押し問答の結果、 私が手術に同意しなかったので
「来週、旦那さんをつれてきてください。」
と言われ
とにかく、病院を出て、ほっとしました。
しかし、事態は深刻なのだということは 十分重く感じていて
帰り道は、気がついたら
娘の手を ぎゅっと握っていました。
「とにかく この子を連れて家に帰らなくては・・・」
いつも通る駅前の風景が色を失って
私だけが違う世界にいるような 実に奇妙な感覚でした。
どの道を通って帰ったのか 記憶もないのですが
帰宅してから、もう一度 落ち着いて考えました。
もし本当にガンならば、子宮だけでなく、私全体がガンなのだろう。
子宮を摘出するのではなくて、私のすべてを 何とかして治さないと・・・。
あの医師が私に直接言ってくれてよかった。
でも、摘出手術はしない。
何か、別の方法を探さないと・・・。
何か、きっとあるはず・・・
そんな思いが グルグルと巡りました。
まず、夫と実家の母親に話しました。
夫は、驚いた上に、私が
「でも手術はしないよ。私、頑張って治すから」
と言うと、
さらに驚いて 二の句が継げない・・・という感じでした。
母親は、ふだんから自然療法を生活に取り入れていたので、
「大丈夫よ、初期なら治るわよ。 がんが治った人、知ってるわよ。」
と、本当に心強い言葉でした。
病院には、それから一度だけ 夫と一緒に行きました。
医師は、ガンの進行状態を説明し、転移の可能性が高いという話もしました。
でも、私がよく話して打ち合わせてあったので、
夫は同意せず
「考えてみます。」 と言ってくれました。
「若いから進行も転移も早いですよ。死んでも知りませんよ!」
と怒鳴られ、夫は かなり不安そうでしたが・・・
「怖い」という気持ち・・
私は、自分自身を 最大限の強気モードにしていたので
「なによ!あれ、脅迫じゃない?」
と、怒ることで
本当の自分の気持ちをごまかしていました。
このときは、自分をごまかしている、なんていう自覚もありませんでしたが。
今だから、わかるんですけど 本当は ものすごく怖かったのです。
でも、「怖い」と言っていては、何も進められないと思って 恐怖心にはフタをして
このときは とにかく前を向いて進むことにしたのです。
もう二度とこの病院には来ないわ!
私には、私の納得できる方法がきっとあるはず・・・これから、それを探すんだ!
それが、見つかったら、「私自身」も見つかるような気がしました。
「なんだか、今の自分は違う」
という感じがしていたのです。
「私」を演じている自分・・・のようなつかみどころのない感覚。
とても微細な感覚ですが、時々、ふっと感じていました。
(この感覚を深く見つめていくことで、後にものすごい宝物を発見しました! → 体験その3)
私は ひとりでテンションを高くしていって、そのなかで わずかな希望を見出していました。
そうするしかなかったからです。
がんと診断されたことは、周囲にはほとんど話しませんでした。
なぜなら
この時代(1990年代)は
がん=死 というイメージで
患者本人には 病名を知らせずに
こっそり家族が病院に呼ばれて告知され
本人には最後まで隠し通して病院で ガン治療を受ける
という常識がありました。
そんな時に
私の「病院治療を受けずに自然療法を行って治す」というやり方は
到底、理解されないだろう。
たぶん、反対意見のほうが大多数だろう。
ということは 自覚していたからです。
「手術しないとダメだ」
なんてマイナスなことを言われたら
一生懸命キープしている気持ちが一気にダウンしてしまいそうで、怖かったからです。
私は 緊張しながら、恐怖にフタをして
ギリギリのところで頑張っていました。
(このときフタをした恐怖感は 後々、しっかりと感じ取るチャンスに恵まれることになります
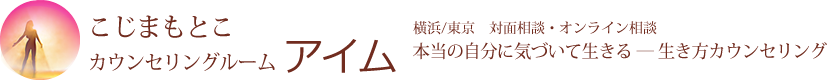








 2度の癌の体験の中で、私自身、いろんなことに気づかされ、自分の生活や考え方を見直しました。それを体験談として伝えることを始めたのをきかっけに、たくさんのがん患者さんからご相談を頂くようになり、ワークショップで伝えることをしてきました。これまでのカウンセリング実績は500人以上。
2度の癌の体験の中で、私自身、いろんなことに気づかされ、自分の生活や考え方を見直しました。それを体験談として伝えることを始めたのをきかっけに、たくさんのがん患者さんからご相談を頂くようになり、ワークショップで伝えることをしてきました。これまでのカウンセリング実績は500人以上。